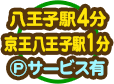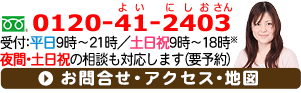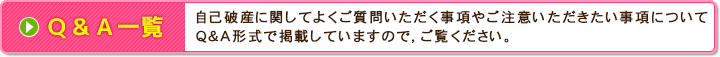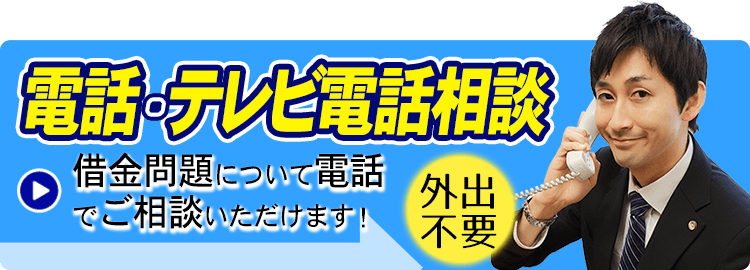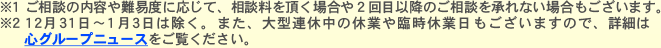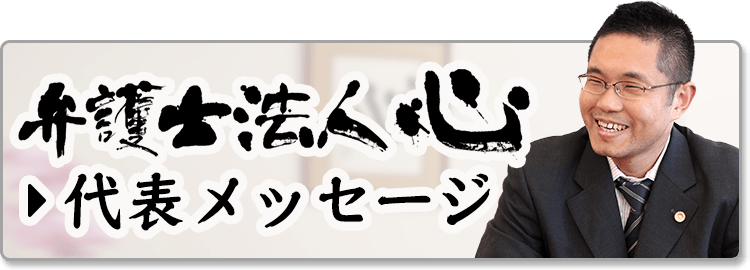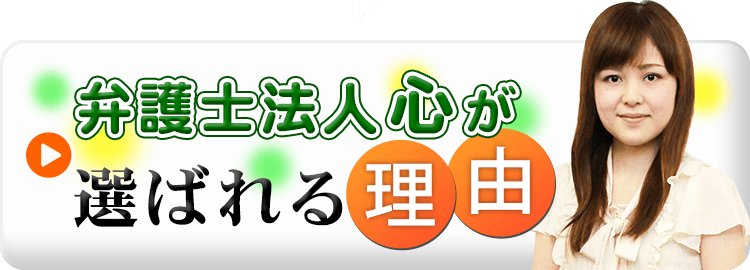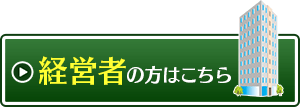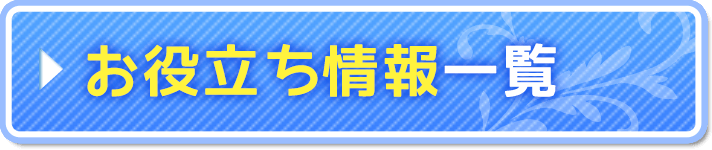お役立ち情報
自己破産は自分でできる?失敗する?手続きや費用について
1 自己破産は弁護士への依頼がおすすめです
自己破産をしたいけれど、弁護士などの専門家に依頼するための費用が工面できないため、「いっそのこと、代理人に頼まずに自分で自己破産手続きを取ることはできないものか」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。
結論から申し上げますと、自己破産手続きをご自身で行うことは可能です。
法律上、「自己破産は必ず弁護士などの代理人を立てなければならない」「一般の方は申立人になれない」という決まりはないためです。
もっとも、労力的な負担や、手続きの正確性、心理面での安心感という観点からは、自己破産は借金問題に精通した弁護士に依頼した方がよいと言えます。
その理由は、以下のとおりです。
2 自己破産を弁護士に依頼すべき理由
⑴ 最終的には費用の節約になる
たしかに、ご自身で申立てをすれば、弁護士費用の出費は避けられます。
しかし、注意しなければならないのは、本人申立ての場合、「管財事件」になる可能性が高いという点です。
自己破産には、裁判所によって破産管財人が選任される「管財事件」と、破産管財人が選任されない「同時廃止」という2つの手続きがあります。
管財事件になった場合、選任された管財人の報酬は、破産者本人の負担となるのが原則です。
弁護士が代理人になっていない場合、破産管財人の費用は、約50万円と高額になることもありますので、結果的に、弁護士に依頼した場合と変わらないかそれ以上の出費になってしまう可能性もあります。
なお、代理人弁護士が付いていない破産事件が管財事件になりやすい背景としては、申立書類の内容に関して、専門家である弁護士による事前のチェックを経ていないことから、裁判所において専門家である弁護士=破産管財人を選任したうえで調査しなければならないことが挙げられます。
裁判所によっては少額管財手続の運用もあり、この手続きであれば予納金の金額も20万円程度と比較的少額で済みますが、この手続きもやはり代理人弁護士が就いていることを前提としています。
管財事件は、代理人弁護士が就いていない場合だけでなく、債務者が一定以上の高額な財産を持っており、財産の処分・配当を行う必要がある場合や、免責不許可事由があり免責の妥当性の判断をするための調査が必要になる場合にも選択されます。
逆に、これらのいずれにも該当しない事件であれば、同時廃止の手続きで処理される可能性が高いといえます。
⑵ 弁護士依頼で債権者の取り立てから解放される
弁護士への依頼後、代理人弁護士が「受任通知」を債権者に送付すると、債権者からの取り立ては止まります。
貸金業法により、弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けた場合、債権者は、それを無視して取立てをすることが禁止されているからです。
個人債権者や商売の取引先など、貸金業法上の規制とは無関係な債権者に関しては、この規制は及びませんが、それでも取り立ての多くが止まるケースがほとんどです。
しかし、ご自身で自己破産手続きを進める場合、このような措置はありません。
自己破産の申立てを行って破産事件受理票が発行され、そのコピーを債権者に送付してようやく、取り立てが止まることになります。
債権者からの日々の督促にお悩みの方にとっては、債権者からの取り立てがすぐに止まるというのは、それだけでも大きなメリットであるといえます。
⑶ 即日面接による手続き期間短縮の可能性
東京地裁では、平成11年より、即日面接制度の運用を行っています。
即日面接制度とは、代理人弁護士が付いて事前準備が整っている破産事件につき、自己破産の申立ての日から遅くとも3日以内に代理人弁護士と裁判官が面接を行うというものです。
弁護士の調査内容に問題が無ければ、面接の当日に破産手続開始決定がされます。
この制度を利用すれば、利用しない場合と比べて、手続きに要する時間を1~2か月程度短縮することが可能ですので、いち早く債務に関する問題を解決することができます。
制度の利用は、代理人が付いて申し立てられた破産事件であることが前提となっており、代理人が付いていない本人申立ての事件に関しては、即日面接制度を利用することができません。
これは、代理人弁護士が必要な調査を申立前に尽くしているはずであるとの信頼を前提にしているためです。
⑷ 破産手続きの手間の軽減
自己破産の必要書類にはご自身で収集しなければならないものも多数ありますが、作成や確認は弁護士に代行してもらうことができます。
弁護士に依頼をすれば、少なくとも書類の不備で度々裁判所へ足を運ぶ必要はありません。
また、ご自身で自己破産をする場合、裁判所への出頭や裁判官との面接などのすべての手続きをご自身で行わなければなりませんが、弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として出席してくれることも多いので、その手間を最低限で済ませることができます。
裁判所が開いているのは平日の昼間なので、ご自身ですべての手続きを行う場合、仕事を休まなければならないケースも出てくるでしょう。
さらに、債権者一覧表の記載などに必要な取引履歴の開示請求など、債権者への連絡を弁護士経由で行ってもらうことが可能です。
3 自己破産を自分でしたい場合によくある質問
⑴ 自己破産を自分でやって失敗したらどうなるか
書類の不備などで自己破産に失敗してしまうと、債務の返済義務はなくならず、経済的に苦しい状態が続いてしまうことになります。
どうしても自己破産できない場合には、個人再生や任意整理などの他の債務整理手続きを行うことで債務に関する問題を解決できることもあります。
⑵ 自己破産を自分でやる場合にかかる費用はどのくらいか
自己破産の申立てを行う場合、少なくとも以下の費用が最初に必要となります。
・ 収入印紙(約1500円分)
・郵便切手代(申立裁判所によって金額は異なり、通常数千円程度)
・官報公告費(裁判所や手続きで異なり、通常1万円〜)
また、管財事件となる場合は、上記に加えて、破産管財人への報酬(概ね50万円~)が必要です。
すでに述べたとおり、弁護士に依頼した場合は、仮に管財事件になったとしても少額管財手続きが選択される可能性があり、その場合は破産管財人の報酬が20万円程度で済むことがあります。
さらに、弁護士に依頼して同時廃止となった場合には、破産管財人への報酬は不要となります。
4 自己破産の相談は当法人へ
「自分で自己破産申立てをしようと思ったが、途中で断念して相談しに来ました」という方もいらっしゃいます。
当法人は、自己破産による借金問題の解決実績が豊富にありますので、書類収集や書類の書き方、管財人対応の仕方など、免責決定が得られるための効果的な方法等のノウハウを有しています。
自己破産をする方にとって「お金がない」という事情はもっともです。
しかし、当法人は債務についてのご相談は原則として無料となっておりますし、弁護士費用の分割払いも可能となっておりますので、どうぞ安心してお電話いただければと思います。
「借金が膨らみ、自分で自己破産手続きを行おうかどうか迷っている」という方は、まずは当法人の弁護士にご相談ください。
自己破産しても没収されない自由財産とは お役立ち情報トップへ戻る